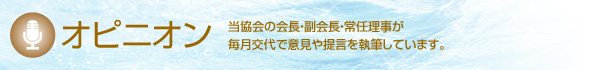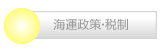2009年5月
景気対策と国内定期航路事業
日本船主協会 常任理事栗林商船株式会社 代表取締役社長

2年前の4月号の本欄で、『国内定期航路事業の現状と今後』というタイトルで当時のフェリー・RO船の抱える悩みを書かせていただいた。当時は今にして思えばまだまだ序の口だった燃料油の価格高騰が、じわりと各航路、各船社に襲い掛かり始め、伸び悩む国内物流量から、航路の再編を余儀なくされた時期であったと思われる。
あれから2年、世界経済が天国と地獄を見る中、景気対策という名の下に新たな問題が国内定期航路業界に持ち上がっている。
国内定期航路業界は外航定期と違い、絶えずトラックや鉄道といった違う輸送モードと直接対決している。競争相手であるトラックは道路を、鉄道は線路をインフラとして使用するわけであるが、そこにはいろいろな形で税金を始めとして莫大な公的資金が注ぎ込まれている。それに対し内航海運は、港の整備として税金が注入されているがそれ以外は全部自前であり、業界としてのバランスで見れば明らかに不公平であると思われる。
昨年秋から始まった突然の金融恐慌により、結果的に日本が先進国の中で一番被害をこうむっているような面も見られるが、それを挽回しようと政府・与党が次々と経済対策や補正予算を打ち出してきている。それはそれで結構なことなのだが、困ったことに国内物流の各輸送モードに使われる税金の差をさらに広げるような、高速道路の割引が大々的に講じられている。
高速道路は貨物輸送を行う大型トラックに対し、深夜割引という形でまず平成16年1月1日から30%レスが実施された。その後昨年の2月15日には40%レスになり、さらに昨年8月29日に発表になった、福田前総理時代の「安心実現のための緊急総合対策」に対応し、昨年10月14日から50%レスへと割引の拡大が行われた訳である。
そして今回、乗用車の休日高速道路千円乗り放題は、金融危機を受けて発表された昨年10月30日の政府・与党発表の「生活対策」に盛り込まれ、その対策を受けて、今年の3月末から乗用車への割引が実施され、ETCを使えばどこまで乗っても千円となったのである。
もちろんどちらの対策も、総合的には今の日本に必要なのは間違いないことで、何とか不景気を打破しようという熱意が伝わってくる。しかしこのような政策も、結果的に物流業界の中で不公平感を助長したり、実際逆モーダルシフト現象を起こしてしまっているだけでなく、いわゆる税のイコールフィッティングに反したりするようでは片手落ちであると思われる。
これらの高速道路割引により、国内定期航路ではフェリーで120億円、RO船とコンテナ船でやはり70億以上の影響がすでに明らかになっている。また、瀬戸内海航路などこの政策により、恒常的に旅客・貨物とも船離れが起きてしまったところもある。
今後わが業界としては、現在審議中の補正予算を財源として、この問題に大々的に巻き返しを図らなければならない。すでに始まった政策を止めることも出来ないし、かといって高速道路割引と同様な対策を取るのも困難であろう。しかし内航定期航路業界の活性化のために、是非とも物流コストの低減という観点から、熱のこもった施策が必要である。
関係各位の努力と、政治行政両面の深い理解をお願いするばかりである。