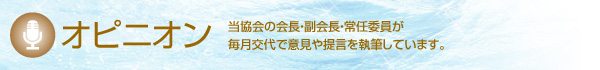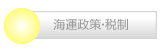2025年5月1日

日本籍船制度の抜本的改善の
必要性について
日本船主協会 副会長商船三井 代表取締役社長
橋本 剛
日本は四方を海に囲まれ、海運業はわが国の経済活動と国民生活において極めて重要な役割を果たしています。輸出入の99.6%を海上輸送が支え、そのうち約7割を日本商船隊が輸送しています。何よりも国民生活に直結するエネルギーや食糧の輸入を担っています。また、国内外の大規模災害時には、邦船社が迅速に対応し、サプライチェーンの維持に貢献してきました。
近年、外航船舶のほとんどをパナマ籍やリベリア籍のような便宜置籍船にしており、国際条約に基づく船舶管理を行っています。日本籍船が選ばれない理由は、制度が明治32年に制定された船舶法に基づいており、外航海運には国際規制があるにも関わらず、設備・検査・船員等に係る日本籍船独自の追加要件や煩雑な手続きが多く課されているためです。船主の方々からは「とにかく世界共通ルールの船にしてほしい。今のままでは持ちたくても日本籍船はとても持てない。」という声を伺うこともあります。
現代の海運業では三国間輸送が拡大し日本に寄港しない船舶が増えており、そのような船に対しても日本籍船では外地において手配し難いHK(日本舶用品検定協会)品の利用が求められ、出来ない場合には国際的に認められているMED(EU舶用機器指令)品を暫定的に搭載した後、日本寄港時にHK品に再度交換する必要も出てきます。
また、無線機器の年次検査においては、他の船籍では現地検査員による検査で直ぐに完了するのに対し、日本籍船では日本から大きな検査機器を持って技師を海外に派遣しての検査が2種類求められています。日本籍船に転籍したことで、乗組員が落水した際に位置を計測する海外製の機器の利用が認められず、やむなく使用不可としている事例も聞いています。これらは国際条約に基づく標準的な船舶管理では考え難い実務であり、海外の船舶管理会社からは驚きの目で見られてしまっているようです。
昨今、米国では、経済安保の観点から自国籍船を増加させる政策の動きが出ています。国際的な規制や政治的な変動により、便宜置籍船の利用が制限されることもないとは言い切れません。このような中で、日本籍船が現状のような「持てない、使えない」船であり続けることは、国にとっても大きな問題だと考えます。
近年、トン数標準税制適用各社に増加要件が課されているため日本籍船は増加傾向にありますが、その努力の余地も限界に達しています。トン数標準税制適用会社以外では外航日本籍船はほぼ選ばれていません。これまで国土交通省も制度運用面で改善に努めて頂いてきておりますが、日本籍船を普通に選ばれる船にするためには、外地で船舶管理をする事も多い外航船舶を国際標準の実務ができるように内航船舶とは分けた制度とするなど、法改正を含めた抜本的な改革が必要です。
エネルギーや食糧を輸入に頼る日本において海運会社が存在することは欠かせません。わが国外航海運の保有船舶の70%以上は日本の造船所で建造されており、造船・舶用技術の発展と海事クラスター全体の振興にも寄与しています。これにより、地域経済の活性化や国防を支える艦船の建造・維持にも貢献しています。
日本籍船制度の抜本的な改善は、日本の経済安全保障、国際競争力の観点からも極めて重要です。海洋立国を目指し大胆な政策を打ち出しているシンガポールのような国とは既に大きな差が生じております。
ぜひ、日本籍船を巡る諸制度について大胆に改革を進めて、日本の海運業が他国と同等な競争ができる環境を整備し、造船業・舶用工業とともに、わが国海事クラスターが力強く維持・発展していくことを強く期待してやみません。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。