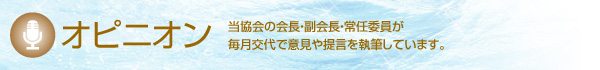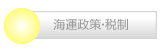2025年7月1日

「米国の関税政策と海運業界」
日本船主協会 常任委員飯野海運 代表取締役社長
大谷 祐介
第二次トランプ政権が誕生してからおおよそ半年になろうとしている。バイデン前政権からの政策転換は多岐にわたるが、「米国第一」を掲げて再選した同大統領は連日のように新聞紙面を賑わしている。中でも世界経済とりわけ海運業界にとって影響が大きいのは「相互関税」の導入と中国をはじめとする各国との交渉の行方、そして米国通商代表部(USTR)による中国建造船に対する入港料の徴収だろう。
学生時代に学んだ記憶をたどれば、国際的な枠組みでは1947年に署名された関税及び貿易に関する一般協定(GATT)や、1995年に設立された世界貿易機関(WTO)が思い出される。これらは、関税の引き下げを通じた自由貿易の促進を目指した結果、貿易や物流に変化をもたらし、事業構造が外部環境に左右される海運業界にも大きな影響を与えてきた。
こうした枠組みの下、特に日本では戦後に製造業が輸出主導で発展する中で、原材料の輸入や製品の輸出需要が増大し、海運業が経済発展の一翼を担う重要な役割を果たしてきた。この間、海運各社は貿易量の拡大による恩恵を受けた一方で、急激な円高による収入の減少や日本人船員の競争力低下による雇用調整など、多方面にわたる困難を乗り越えてきた。
トランプ政権による経済政策は世界に大きな影響を及ぼそうとしている。今回の相互関税導入は、単なる一国の政策変更にとどまらず、グローバルな物流構造に影響を及ぼしかねず、従来の貿易ルートが大きく変わる可能性がある。果たしてそれが海運各社にどのような影響を及ぼすのか、まだまだ答えは見えてこない。
飯野海運の外航船隊への影響においては、米国寄港の割合は、他社と比べればかなり少ないのかもしれないが、近年ではシェールガスから産出されるLPGを積載するため、当社VLGCはヒューストンなど米国湾岸の各港に入港している。
海運各社の歩みは、米国の経済政策の変化がもたらす様々な困難に繰り返し適応してきた歴史でもある。一方で米国はわが国の同盟国であり、大事なパートナーでもある。
歴史が教えてくれるのは、状況に対応し、変化を機会へと転じる力こそが、持続可能な成長を支える土台となるという事実だろう。ここ数年の間にも、新型コロナウイルス感染症の世界的流行、ロシアによるウクライナ侵攻、紅海情勢の悪化による同海域の迂回など世界経済へ大きな影響を与える事象が次々と発生したが、そのたびに海運各社は柔軟に対応してきた。
不確実性が高いといわれる現代においても、海運が世界をつなぐインフラとして社会に価値を提供し続けるためには、過去の経験を糧に変化を恐れることなく挑戦し続けることが求められる。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。