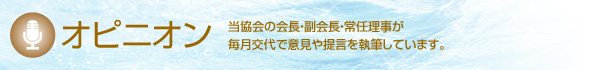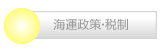2011年9月

エネルギーの
中東依存リスクの軽減を
日本船主協会 副会長日本郵船株式会社 代表取締役社長
工藤 泰三
東日本大震災で犠牲となった方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また、被災された皆様の一日も早い復興に全国民の力を合せたいと念願しております。
ことわざに「全ての玉子を一つの籠に入れるな」というものがあります。今回の東日本大震災でのサプライチェーン危機を通じて、日本企業は分散によるリスク管理の大切さを改めて学んだと思います。今後は日本国内のみならず世界的な規模でサプライチェーンの複線化が進むでしょう。物流企業にとって大きなビジネスチャンスが生まれることと期待しています。
一方、エネルギーに目を転じると、わが国のエネルギー基本計画は昨年6月に原子力発電の強化・化石エネルギーの自主開発権益拡大による自主エネルギー比率の70%化とゼロエミッション発電比率の70%化を柱に改定されたばかりですが、今回の原発事故を受けて再改訂を余儀なくされ、石油で9割弱に達するわが国エネルギーの中東依存度は減りそうもありません。大震災による増分は石油で12?15万B/D、LNGで990?1,220万トンと見積もられ(日本エネルギー経済研究所)、短期的な原子力の代替は主としてLNGに求められています。中期的にはシェールガスの商業生産など非中東ソースの開発が進むでしょうが、現状で輸出余力があるのはカタールで、エネルギーという大切な玉子の多くが中東という一つの籠に入っています。
しかし、チュニジアに端を発し、エジプト・リビアを呑み込んだジャスミン革命の波はパレスチナ・イエメンから湾岸諸国やイランに及んでおり、ただでさえ複雑な中東の政情は一層不安定なものになっています。加えて、私たち海運会社が担う海上輸送も昨年秋のホルムズ海峡でのタンカーへの爆発物攻撃など具体的な事件が発生していますし、何よりもインド洋に拡大しているソマリア海賊の脅威があります。わが国のエネルギーが依然として中東に高く依存し続けることのリスクを懸念せざるを得ません。
エネルギーは、国際競争力の鍵である一方、経済的安全保障の基です。わが国の復興と繁栄には、安全で環境に優しく、経済的なエネルギーを確実に調達することが必要です。日本のエネルギー基本計画の改定が冷静かつ客観的なデータに基づいて行われることを強く希望する所以です。
つい先日、国際エネルギー機関(IEA)の田中信男事務局長が3.11以後のエネルギー展望として、大変興味深い報告を発表されました。 (1)シェールガスの開発によって2035年には天然ガスが石油並みの一次エネルギー源となり、米国・カナダ・豪州がガス輸出国となり得る、(2)エネルギー自給率が低い国々には原子力が安全確保を前提に重要なオプションであり続ける、(3)日本は再生可能エネルギーの活用ポテンシャルが高く、電力供給網やガスパイプラインの接続による改善余地が大きい、(4)日本の省エネルギー技術の一層の深化がエネルギー政策の大きな柱となろうというものです。
エネルギー基本計画の再改訂では、こうした知恵に基づき、日本にとって最良なエネルギーミックスとそれを実現する方策を国民に分かりやすく説明して頂きたいと思います。また、私たちも世界各国からの海上輸送路の安全確保がその基礎にあることを強調して行きましょう。