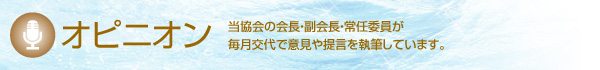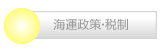2014年10月1日

周回遅れの日本経済
日本船主協会 常任委員栗林商船 代表取締役社長
栗林 宏吉
雨の多い夏であった。昨年同様の猛暑が予想されたにもかかわらず、これだけの雨が特に西日本を中心に降ったことにより、災害報道ばかりで盛り上がりに欠ける夏となった。特に大規模な土石流に遭われた広島市の皆さんにはお見舞いとお悔みを申し上げる次第である。
本稿を執筆するにあたり、前回何を書いたか振り返ってみたところ、ほとんど同じ時期にもたつく日本経済と、当時表面化した福島原発の汚染水問題について憂いて書いていた。さて一年経って、残念ながら世の中どうも事態はあまり進展していないのではないか。いわゆるアベノミクスの第三の矢といわれる経済政策も、いくつかメニューがあるものの、国の方向性を国民に示し納得させるだけの物はまだ無く、時間の経過だけを感じてしまう。
経済政策に目新しいものが決められない中で、既に決まっていた消費税の税率アップのほか、特定秘密保護法、さらには集団的自衛権の行使容認へ向けた閣議決定と、あまり国民経済に関係ないことばかりどんどん決まっていくのは不思議である。
それでは外交面ではどうかというと、戦後レジームから脱却し強い日本を取り戻すために、積極的平和主義により地球儀外交を行っているようではあるが、肝心の近隣諸国との関係がこれだけ悪化してしまうと、その努力も半減といったところであろうか。平和な海を、国民経済発展のために航行する日本の海運が、役割を替えずにいられる事を願うばかりである。
さて第二次安倍内閣は、少子化というよりは人口減少問題を、地方経済の再生と女性の活用で歯止めをかけたいという意気込みが感じられる。この問題は、内航海運の船員不足問題にも現れているように、日本の各地各業界で顕在化しており、日本経済の勢いを弱めるボトルネックとなっており、非常に重要な問題である。
ただ少子化問題は、2003年に担当大臣をおいてからさしたる成果はなく、地域経済の再生も内航海運に代表されるように、ほとんどの地方の中小企業が直接的・間接的に大企業と取引しており、その大企業が国際競争力と利益を重視する姿勢を変えずに海外展開を続ける以上、創世といういつか聞いた言葉を使ってもなかなか大変だが、何とか解決の道筋をつけなければならない。現状を受け入れ、これからの時代に合った生き方、働き方を見出し、それを社会全体でサポートする体制を構築できるかが重要な点となろう。
成長の名の下に目先の利益と効率を追い求めるのか、長期的な人口減少に歯止めをかけるため社会の仕組みを変えていくことを優先するのか、それとも両方出来るのかどちらもダメになるのか、興味と期待を持って舵取りを見守りたいと思う。