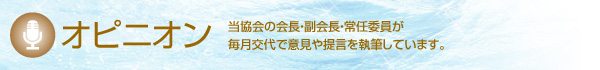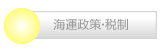2017年12月1日

海運における
デジタライゼーションへの
取り組み
日本船主協会 副会長日本郵船 代表取締役社長
内藤 忠顕
現在は、様々な分野でのITの活用とそれによる改革が働き方や産業の在り方自体にまで及びつつあり、第四次産業革命とも言われています。その中でもデジタライゼーションは次の社会につながる波として世界の大きな潮流となっており、もはや避けて通ることはできません。海運におけるデジタライゼーションについては様々な場面で議論が進んでおり、IoTとICT(情報通信技術)の進化によりもたらされたビッグデータをどのようにビジネスに活かしていくのかについては、関係者の関心も非常に高まっていると感じています。
海運業でのビッグデータ活用の事例としては、まず運航や船舶管理の現場を見える化し、効率化を推し進める動きが挙げられます。船陸間の通信技術の進化はビッグデータの活用を促進し、衝突予測技術などによる事故軽減や、パターン解析による配船の最適化などのように海運の現場を変革する力を秘めています。これらに加え、申告書類のデジタル化や、顧客とのデータ・システムのネットワーク化など、デジタライゼーションの波が業界全体に及んでいき、さらにそのデータを利用した新たなサービスが生まれるといった連鎖が広がっていくことでしょう。
ビッグデータの活用やIoTの進化により様々な改善が進んでいますが、その最も大きなドライバーはユーザー側の細かな視点やニーズであり、それを具現化するICTです。これは海運業に限ったことではないかもしれませんが、ビジネスの全体像と現場の具体的な課題を知るユーザーが、ICTに長けたプレイヤーと連携することで具現化し、改善を継続することが大切だと考えています。これらの対応は、各社が独自に進めていく施策が必要である一方で、単独の企業がユーザーのすべてのニーズに応えるソリューションを提供することは難しいでしょう。
今年トライアル実施が予定される、日本海事協会のシップデータセンターなどのオープンプラットフォームに対しても大きな期待が寄せられています。また、研究が進み注目が集まる自律運航についても、これらの実現やルール作りにおいてオープンプラットフォームの活用が不可欠であると考えます。
デジタライゼーションの波は、国や業界の垣根を越え世界中を席巻しています。海運業界としてこれまでの歴史で培った経験を活かしながら、社会の新しいニーズに応えるべく、その流れに乗る必要があると考えています。そのためにも、それぞれの強みを活かしながら現場の力、ICT、そしてパートナーシップを活用し次の社会に向かう必要があるのではないでしょうか。
以上