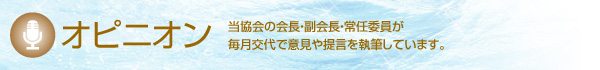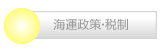2024年7月1日

小型バルカーに
環境対応船型って必要ですか?
日本船主協会 常任委員商船三井ドライバルク 代表取締役社長
平田 浩一
ドライバルク輸送領域においては、ケープサイズ・カムサマックスでは先行してLNGやメタノールとの二元燃料船が導入され、さらにはアンモニア燃料利用が検討される等、環境対応船への取り組みが加速されています。一方、スープラマックス以下の小型バルカー領域では、技術やコスト負担の制約等からハードルが高く、また、お客さまも自社のスコープ1領域での温暖化ガス削減に取り組んでおられ海上輸送等のスコープ3にはまださほど積極的ではないとの声が聞かれることもあり、結果的に環境対応船の導入は遅々として進んでいないのが現状かと思います。
気候変動問題関連規制の海運業への導入状況に目を向けると、2023年開催のCOP28で化石燃料の段階的廃止に向けたロードマップが承認され、欧州では本年からEU-ETSの海運セクターへの適用も始まり、来年にはGHG排出強度上限・罰則規定を伴うFuelEU Maritime導入も控えています。また、今後の重油規制動向には特に注目が必要であり、昨年のMEPC80にて議論された重油焚き船への課金・代替燃料船への再分配等の経済的手法が今後制度化されることで、VLSFOと代替燃料間に調整作用が働き、将来の両燃料の価格帯が近似していくシナリオも想定されます。
小型バルカーのお客さまの多くの事業では自社の製造・精錬プロセスで温暖化ガスが排出されており、低炭素原燃料への転換、CO2の回収、カーボンクレジット調達・創出等々、課題解決にインテンシブに取り組んでおられます。例をあげれば枚挙にいとまがありませんが、鉄鋼産業における還元鉄利用拡大、セメント産業での自社排出CO2の回収とメタネーション技術の組み合わせによる都市ガスとしての再利用、食料分野では畜産業におけるメタンの回収/再利用等々、実に様々です。
一方、消費地の近くに生産拠点を設けることで、地産地消を通じ低炭素化を推進できるお客さまもおられるものの、原燃料供給地・自社製造拠点・消費地間の空間的な隔たりを海上輸送で結び付けなければならないお客さまも数多く存在します。また多くのお客さまはステークホルダー・社会に対し自社のESG推進状況を継続的に報告していく責任を負っておられます。従い、今後気候変動問題への社会の対応が深度化するにつれ、お客さまがサステイナブルに事業を行っていくうえで環境対応と経済性の両立がさらに一層志向されていくことになるなか、いずれスコープ3、即ち小型バルカーによる海上輸送においても「環境対応」が強く求められることは必然と考えます。
しかしながら現状では、小型バルカー領域では、気候変動問題と私たちのビジネスの関係性やその影響等について十分に理解が追い付いていない、或いは、敢えて正面からは捉えようとしていないという側面が否めない、ように感じます。確かに、小型バルカーという船型がゆえの様々な技術課題を如何にクリアすべきか、代替燃料を追求すべきか風力推進補助装置を選択すべきか或いはその両方か、増加コストはどのように分担するべきか、等、諸事万端不確実にして手探りのなかでひとつひとつを決断するには困難を極めます。
であるからこそ、自ら知恵を絞り工夫を凝らしお客さまにスコープ3への意識を高めていただくこと、船型開発に柔軟に取り組んでいただいている造船業界の皆さまとしっかりと連携していくこと、そして、サプライチェーン全体でソリューションを共創し且つそれらをリードしていくこと、が社会インフラ産業たる海運業としての責務であろうと考えます。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。