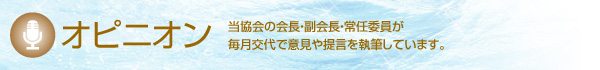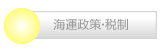2024年10月1日

「人手不足を乗り越えるために」
日本船主協会 副会長栗林商船 代表取締役社長
栗林 宏𠮷
あらゆる業界で人手不足が問題となっている中で、内航の船員不足も例外ではない。日本を襲う急速な少子化の波は、これからもさらに大きなうねりとなって、内航業界に向かい続けるであろう。
今後の国内物流は、内航の大宗貨物の鉄鋼、石油、セメント等の輸送量は近年の漸減傾向が続いて行くと考えられる。しかし減っていくとは言え日本の国内物流の約40%というシェアがあまり変わらないことを考慮すると、結構な物量を少ない船員でいかに効率的に輸送するか、更に真剣に考えていく必要がある。
現在の内航行政の取り組みとしては従来の船員の確保育成と同時に、いわゆる船員の働き方改革として改正船員法を遵守し、労働環境や職場環境を改善して内航船員を魅力ある職業とすることにより、少しでも船員不足を補おうとしている。勿論そのために、荷主業界と海運界との対話を取り持ち、法改正に伴う環境整備に尽力していただいている事には感謝しなければならないが、今後さらに進む船員不足に対処するために従来のやり方や仕組みを大きく変えるところまでには至っていない。
業界として今後見直していかなければならない点は、内航貨物船の仕様や船型だろう。究極的には自動運航船となり、船員数が激減することが理想であるが、それまでにも大型化と省人化が必須である。現在内航貨物船5,000隻と言われているが、100総トン未満の小型船が約1,600隻あり、それ以外のいわゆる貨物船は最新の統計によれば、3,396隻、431万1,893総トンとなっており、平成26年の数値と比較すると隻数で65隻減少しているが、全体の総トン数では74万8,000トン以上増加し、平均総トン数も1,029トンから1,269トンへと23%程度増加していて、業界としては大型化が進展していることがわかる。また内航の標準船型である499総トン型に絞ってみてみると、平成26年と直近の令和6年3月では21隻増加している。大型船(特に6,500総トン以上)が隻数を伸ばし業界全体の大型化に寄与している中で、この船型も健闘しているのは、業界の慣習として適した船型であることや、法律上小型船としての恩恵を得ていることが挙げられる。やはり単純に標準船型を大型化して効率化を追求できない内航独自の要素があると理解すべきだろう。
そうなると残るは仕様の改善で省力化、省人化がどこまで進められるかという問題となる。この問題は内航のGX、DX化の流れもあり、内航ミライ研究会等が省エネ、省人化のコンセプトを発表している。ただこれらは時代に即した考え方ではあるが、本当に定員の削減につながる裏付けはまだない。これは行政が省人化に対して本格的に向き合っていないからだと思われる。
過去には限定近海船においては平成16年8月から始まった「次世代内航船乗組み制度研究会」で検討され導入された「高度船舶安全管理システム」のように機関部の定員の見直しにつながるような改正が、さらに遡れば外航船の競争力低下を防ぐため、昭和57年に船員制度の近代化を目的とした船員2法の改正があり、それに応じて昭和58年には近代化船の要件を規定する「船舶自動化設備特殊規則」が規定された。この規定の制定には、当時の海運局、船員局、船舶局が協力して全日海と協議し、省力化設備の搭載等を義務付けて省人化を図ったと伺っている。このような対応が無ければコンセプトは現実化しない。
内航も省力化、省人化のコンセプトを具現化した「次世代内航近代化船」が必要である。
行政の本気度が問われてくる局面である。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。