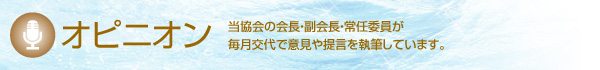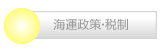2024年12月1日

「外航日本人船員(海技者)
確保・育成スキーム」を
ご存じですか?
日本船主協会 副会長国際船員労務協会 会長
井上 登志仁
外航日本人船員(海技者)の確保育成はわれわれの重要課題の一つであり、これまでにそのための諸施策が導入・実施されてきたが、首題のスキームもその一つである。2008年にスタートし、2014年に実施した衣替えを経て現在も継続中の息の長い制度だが、筆者の印象では認知度がもう一つ上がっていないように思われるため、この場を借りて取り上げたい。
そもそも本スキームの導入は、2005年に労使共同で国に対して行った申入れ、即ち、新規に登録される日本籍船について、当時の国際船舶に適用された船・機長の配乗要件の制限の撤廃(=外国人船員の全乗の容認)を国土交通省に申入れたことに端を発する。この配乗要件の撤廃と一対を成す課題として検討されたのが本スキームの導入である。このような背景もあって、本スキームは官労使による取組みであり、国からの補助金とIBF労働協約に基づく基金によって全体の費用が賄われている。運営は、国土交通省、全日本海員組合、日本船主協会および国際船員労務協会の4者で構成する「外航日本人船員(海技者)確保・育成推進協議会」(以下、推進協議会)が行い、事務局は日本船員雇用促進センター(SECOJ)が務める。
冒頭で触れた通り、本スキームは2008年に開始後、2014年に現在の形に改善された。旧スキームでは、参加者に対して推進協議会が実施した面接に合格した者が最初の一年間で海技大学校等での陸上研修および商船による乗船実習を受け、2年目以降は推進協議会が船舶職員として適正ありと評価した者のみ原則三航士・三機士として最長5年目まで商船に乗組み、就職を目指す形を取った。拘束期間が長く、最終的に就職を勝ち取れるか保証がないこと、就職先は自身が乗船している船舶と関連する企業に自ずと限定されるなど問題が多く、見直しが議論・検討された結果、2014年に現行制度に変更された。
現行制度では、採用希望者である企業と就職希望者である三級海技士資格受有者(含む予定者)との合同面談会を開催し、就職希望者が研修生として一年間の陸上および海上での研修を受けた後に就職することを前提として両者の間でマッチングが成立した場合に限り、国からの補助金およびIBF労働協約関連基金によって当該研修やそれに付随する費用が賄われる制度である。合同面談会で企業と就職希望者が即戦力としての採用をその場で合意すれば、当該研修の対象外となる。本スキームの対象となる就職希望者については、原則30歳までとしていることもあり、新卒者だけでなく、一旦就職したものの、転職を希望する者もいる。
本スキームの定員は年間20名程度だが、これまでこの枠に達したことはなく、財務省から厳しい指摘を受けた結果、国からの補助金は削減されることになった。これを受けて推進協議会は、陸上研修、乗船研修の効率化や訓練内容の見直し、認知度のアップや参加者の拡大を目指した広報活動の強化に取り組んでいる。因みに、これまでの実績(2024年3月1日現在)は、旧スキーム(2008~2013年)が参加者98名に対し、外航海運企業への就職者数が53名(平均8.83名/年)、現行スキーム(2014~2023年)が参加者189名に対し、同就職者数が174名(平均17.4名/年)となった。
現行スキームに衣替えして合同面談会の開催によるマッチング方式を採用したことにより、使い勝手が格段によくなり、採用増に結び付いた。しかし、参加企業数は限定的であり、合同面談会に参加する就職希望者の数も必ずしも安定的ではない印象を受ける。本スキームが魅力を増し、更に有効に活用され、日本人船員の確保により一層貢献することを期待する。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。