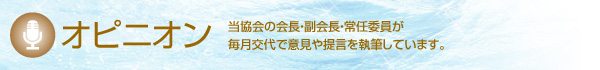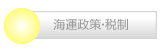2025年1月1日

2025年新春を迎えて
日本船主協会 会長明珍 幸一
新年あけましておめでとうございます。
2025年の年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。
昨年は、中東や紅海を巡る情勢の悪化により、当協会会員会社の運航船舶は、スエズ運河に繋がる紅海の航行を回避して喜望峰経由へ迂回せざるをえない状況が常態化した他、ロシアのウクライナ侵攻長期化等の地政学リスクによって、経済安全保障の観点からも、海上輸送を通じて物流の多くを担うわれわれ海運の重要性が改めて認識された1年でした。
またEU-ETS(欧州域内排出量取引制度)の海運セクターへの適用が開始され、国際海事機関(IMO)におけるGHG排出削減の為の中期対策の議論も進む等、環境規制への対応も一気に進展し始めた年でもありました。
本年は米国トランプ次期大統領による通商・エネルギー政策の動向、上述の地政学リスク等をはじめとして、海運を取り巻く情勢は不確実性が高い状態が継続することが予想されます。業界としても、これまでの経験や従来のやり方を踏襲するだけでは対応が難しい状況に直面していますが、わが国の暮らしと経済を支える海運業としてその使命を果たすべく、当協会は、本年も業界をめぐる諸課題に着実に取り組んでまいります。
まずは、船舶の安全運航の確保です。船舶の航行の自由と安全の確保は、海運業界にとって安全で安定的な海上輸送サービスの提供における大前提です。2023年10月のイスラエルとハマスの軍事衝突以降、紅海周辺海域ではイエメンの武装勢力ホーシー派による民間商船を標的とした攻撃が続いています。当協会会員会社の運航船舶がハイジャックされ、乗組員全員と船舶が拘留されてから1年以上が経過しましたが、同船は未だ解放されておらず、拘束されている乗組員の精神的な苦痛は相当なものであると心配しています。本船と乗組員の一日も早い解放を強く望みます。
民間商船への攻撃や不審船追尾などの事案は、イスラエルとは無関係な船舶も含めこれまでに130件以上発生しており、2隻が沈没、4名の船員が犠牲になる等、周辺海域の治安の悪化に伴い、世界のライフラインを支える商船の安全運航は大きく脅かされています。当協会は、こうした非道な行為を断固非難するとともに、一刻も早く船舶の自由かつ安全な航行が確保されるよう、引き続き強く求めたいと思います。
こうした紅海情勢に呼応するかのように、ソマリア沖・アデン湾海域での海賊事案が増加し始めており、事態を大変憂慮しています。わが国自衛隊や海上保安庁および各国政府が協調した海賊対処行動は引き続き必要不可欠ですので、厳しい環境下での護衛活動に深く感謝申し上げると共に、活動継続へのご支援をお願い申し上げます。
次に、環境問題・規制への対応です。世界の海を舞台に活躍する海運業界にとって、気候変動対策としてのGHG削減・脱炭素への対応は、最重要課題の一つです。当協会はIMOに先駆けて「2050年GHGネットゼロへの挑戦」を表明していますが、本年も果敢に挑戦してまいります。
現在IMOでは、2023年に採択された「2023 IMO GHG削減戦略」の達成に向けた具体的な規制(中期対策)と、それらを反映する条約改正案が議論されています。一方、EUでは、昨年1月1日に海運セクターに適用開始となった欧州域内排出量取引制度(EU-ETS)に加え、本年1月1日からは、船舶の使用燃料のGHG強度に係るFuelEU Maritime規制の適用が始まる等、IMOの動きに先行して地域規制の導入が進んでいます。海上輸送の安定やグローバルなサプライチェーンの維持において、統一的な国際規制の整備により地域規制の乱立を防ぐことが肝要であることは明白です。国際規制の議論を着実に進めることが、より重要な意味合いを持つ中、引き続き日本政府がIMOでの議論をリードしていくことを期待すると共に、海運業界としてもバックアップしていく所存です。
一方、IMOの目標達成には、新燃料・新技術の開発や新たな燃料の供給体制の構築に向け、業界や立場を越えて連携した抜本的な取り組みや体制作りが欠かせません。昨年8月末には、海運大手3社と国内造船4社が、液化CO2輸送船の標準仕様・船型の確立に向けた共同検討を開始し、将来的にはアンモニア燃料等の脱炭素技術を活用した新燃料船の設計・開発・建造に係る協業も視野に入れています。わが国海事クラスターを担う海運・造船の両業界が、タッグを組んで厳しい国際競争に立ち向かう大きな一歩だと考えています。こうした業界の垣根を超えた連携の輪が拡がり、わが国海事産業における脱炭素の取り組みが飛躍的に発展することを期待しています。
また、海運を目指す人材の確保と育成も重要な課題です。日本の海運は優秀な日本人海技者によって支えられており、前述の環境や安全の取り組みを実施する際の“核”となる存在です。少子化が進み、他産業と激しい人材獲得競争に晒されている中、わが国海運の安全を支え、国際競争力を維持・強化する上でもその確保と育成は極めて重要です。当協会は、産官学による海技人材の確保・育成のあり方の検討に参画し、関係者との連携を強化して業界としての要望を反映しながら、船員不足、後継者の確保・育成等に係る諸課題に取り組んでまいります。
さらに、次世代を担う若者に海運に対する興味や関心を持ってもらい、未来の海運業界を担う仲間となっていただくことも大切です。本年も1月に「“開運”じゃなくて、“海運”です。」をキャッチフレーズとするPRキャンペーンを全国で実施する他、施設見学や出前授業等の草の根の広報活動も通じて、海事産業の重要性に関する認知度向上と海運への理解を深めていただけるよう取り組んでまいります。
最後に、海運業界を取り巻く情勢が日々刻々と変化し、先行き不透明な状態が続く今日、従来以上に様々なリスクや事業環境の変化に備える必要があります。近年、とりわけその重要度が増している経済安全保障の観点から、わが国商船隊の国際競争力の維持・強化は必要不可欠です。来年3月には、「外航船舶の特別償却制度および買換特例制度」が期限を迎えます。わが国商船隊が、持続可能で安全で安定的な海上輸送サービスを提供し続け、国民生活を支えるインフラとしての使命を果たすことができるよう、海事局をはじめとする関係の皆様と連携の上、両制度の確保に向けた対応を進めてまいります。
当協会の活動に対しまして、本年も引き続き皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上