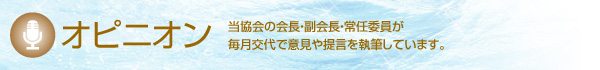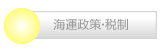2025年8月1日

環境対応と人材育成による
海運業界の持続的発展に向けて
日本船主協会 副会長ENEOSオーシャン 代表取締役社長
片岡 尚
日本船主協会の副会長を拝命いたしました片岡です。海運業界が益々重要な役割を果たす中、重責を担うこととなり、身が引き締まる思いでおります。これまで協会において積み重ねられてきた取り組みをしっかりと引き継ぎ、微力ながら業界の発展に尽力してまいる所存です。関係各位におかれましては、引き続きのご指導とご鞭撻を賜りますよう、この場をお借りしてお願い申し上げます。
周知のとおり、海運業界は環境分野で転換期に差し掛かろうとしています。2025年4月に開催された国際海事機関の第83回海洋環境保護委員会において、GHG削減戦略の中期対策として「使用燃料のGHG強度規制」の導入が合意されました。この新たな制度では、ゼロエミッション船などへの支援や拠出金制度の導入も予定されております。これにより、運航計画、船舶建造投資、燃料調達のあり方を根本的に見直すことが求められる局面を迎えています。
環境規制への対応は、一時的には事業者に大きな負担を強いるものです。しかし、それを単なるリスクと捉えるのではなく、新たな技術や事業モデルを取り込む「機会」として捉えることもあろうかと思います。脱炭素化の潮流に的確に対応し、時宜を得て将来を見据えた戦略的な投資と行動を選び取ることが、国際競争力の維持と持続的な成長を実現する鍵となります。
海運はエネルギー・食料・原材料など、人々の暮らしを支える物資を運ぶ社会インフラの中核を担っています。だからこそ、いかなる時代においても物流を止めない「レジリエンス(強靭性)」を備えることが求められています。変化に柔軟に対応し、安定的かつ持続可能な輸送体制を築くことは私たち業界の責務です。
その基盤となるのは、やはり「人」の力です。船舶の安全・安定運航は船員や陸上スタッフの高度な知識と経験に支えられています。新たな規制に適応するためには技術革新が不可欠ですが、それを現場で運用し、的確な判断を下すのは常に「人」です。GHG削減戦略の実行には新燃料に対応した船舶の導入もありますが、陸上・海上双方における人材育成と安全に関するノウハウの蓄積が不可欠です。
近年は、デジタル化や通信技術の進展により業務の高度化が進み、求められる人材像も変化しています。専門知識に加え、柔軟な思考力や高いコミュニケーション力、自ら考え行動する主体性を備えた人材こそが、これからの海運業を支える柱となるでしょう。変化が激しく、不確実性の高い時代にあっては、状況に応じて自ら判断し、柔軟に行動する力こそが、組織の強さとなります。私自身も、そのような視点を大切にしながら、業界の発展と安全・安定輸送の実現に貢献してまいります。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。