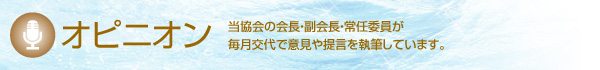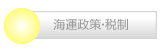2025年9月1日

総合物流施策大綱の変遷と
内航海運
日本船主協会 副会長栗林商船 代表取締役社長
栗林 宏𠮷
政府は令和3年6月に策定した総合物流施策大綱が今年度で終了することから、2030年度に向けた次期の大綱を策定するため、有識者や関係者を構成員として検討会を立ち上げ、その検討が続いている。今回小職が初めてその検討会の構成員をお受けするにあたり、過去の総合物流施策大綱に内航海運についてどのような記述があり扱われてきたか興味があり、過去の大綱に目を通すこととした。
最初の大綱は平成9年4月の閣議決定で、時代背景としては橋本内閣でまだバブル崩壊の混乱から抜け出せず、秋には拓銀や山一証券が破綻するという時代に作られたこともあり、グローバル化が進む世界経済の中で日本が高コスト等を理由に競争力の低下がないようにすることが目標とされ、そのための社会資本整備や規制緩和、商慣行の改善が述べられている。内航海運には、当時まだ続いていた船腹調整事業を、規制緩和推進計画に沿って計画的解消を図る、という記述や、内航海運の一層の効率化を図るために、船舶の大型化、近代化、全天候バースの整備や配船の共同化といった記載も見受けられる。さらに地域間物流としてマルチモーダル施策を推進し、複合一貫輸送により低廉なコストと環境負荷の低減をすでに推奨しており、努力目標として、21世紀初頭までに複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルへの陸上輸送半日往復圏の人口カバー率を約9割とすることが掲げられている。またトラックの積載率についても約5割を目指すことや、パレタイズ可能貨物のパレタイズ比率を9割に向上させることなど、現在2024年問題で議論している事柄がいくつも登場するのは興味深い。
次の大綱は平成13年7月に第一次小泉内閣で閣議決定されているが、その年の1月に中央省庁の再編があり、国土交通省になって最初の大綱となる。内容としては前回の大綱のフォローアップの色彩が強いが、平成9年末にCOP3が京都で開かれ、いわゆる京都議定書が締結されたこともあり、地球温暖化問題への対応という新しい項目が設けられ、環境負荷低減の見地からモーダルシフトを推進し、鉄道・内航合わせてのモーダルシフト化率を2010年までに50%を超える水準を目指すと謳っている。また行政手続きの簡素化・効率化という項目には現在も問題となっている特殊車両通行申請手続きの電子化、ワンストップサービス化の推進が掲げられており、いろいろ考えさせられる。
次の平成17年(2005年)大綱から国際物流に対するウェイトが高くなり、グローバルサプライチェーンにどう対応するかということで、内航の記述も内航フィーダー船に関するものが中心となる。この書きぶりは次の2009年大綱、2013年大綱まで続いていく。
雰囲気が変わる2017年大綱は第3次安倍内閣の時に閣議決定されている。この時期は政権も経済も安定してはいるが、ひたひたと忍び寄る人口減少社会にどう対応するかという記述が随所にみられ、逆に内航フィーダーについての記載はなくなっている。
直近の大綱が令和になって菅内閣で作られた2021年大綱である。ここではコロナの混乱もあり、人口減少社会の中で社会インフラとしての物流の重要性が改めて強調されている。さらにトラックドライバーの時間外労働規制が2024年から罰則付きで導入されることを意識して、「担い手にやさしい物流」の実現に向けてという項目が出現している。
内航についてであるが、一貫して記載があるのはモーダルシフトについてである。その他に、船腹調整制度や暫定措置事業の終了といった大きな政策の節目や、船員の働き方改革、確保・育成について触れた大綱もあった。
モーダルシフトは当初の、コストが低廉でエネルギー消費が抑制できるから推進するという書きぶりから、温暖化対策にウェイトが置かれるようになる。2021年大綱でもトラックドライバーの労働時間規制強化には、トラック業界の生産性の向上や自動化などで立ち向かうという書きぶりで、海運や鉄道へのモーダルシフト化率を増加させるという記載はない。
現在検討中の次期大綱では、最初の大綱にあったような高い目標を掲げ、国内物流の一つの柱として記載されるのではと勝手に予想しているところである。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。