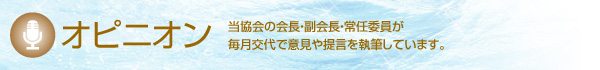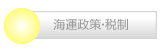2025年10月1日

2018年の改正商法と
定期傭船契約
日本船主協会 常任委員商船三井ドライバルク 代表取締役社長
福井 利明
2018年の商法改正(2019年4月1日施行)により、「定期傭船契約」に関する条文が商法第704条以下に初めて明文化されました。定期傭船契約は、19世紀前半の英国にてその萌芽を見て、1840年代には実務で確立したといわれています。その後、BALTIME(1909)やNYPE(1913)などの標準書式が整備され、現在に至るまで海運実務で広く使われてきました。しかし、日本の商法では長らく、船舶賃貸借契約(裸傭船契約)と航海傭船契約が規定されているのみで、定期傭船契約には明確な規定が存在していませんでした。
もっとも、外航海運の現場では英国法を準拠法とし、NYPEなど国際標準化された契約書式が用いられるのが一般的です。そのため、2018年の法改正が直ちに実務に大きな影響を与える場面は限られるかもしれません。しかしながら、日本法上で定期傭船契約が位置づけられた意義は小さくありません。内航海運はもちろんですが、外航海運でも日本法準拠を選択するケースでは、契約書の作成やリスク評価の際に、今後の重要な指針となるでしょう。
焦点となるのは「事故で第三者に損害が生じたときに誰が法的責任を負うのか。船主か、それとも定期傭船者か」の問題です。2018年改正商法でも、解決を示す明文の規定は置かれませんでした。この点については、戦前の大審院時代の判例が船舶賃貸借の規定を類推適用して定期傭船者の責任を認めており、学説も分かれていました。現在では、定期傭船の法的性質を定めて結論を導く考え方はとられておらず、その代表例が1992年の最高裁判決です。ここでは、契約書上は定期傭船であっても、実際の運航指示や管理の実態によっては傭船者が責任を負う可能性があると判断されました。法的性質よりも現実の業務運用の態様を重視する考え方であり、今日に至るまで学説や法律実務で高く評価されています。したがって、定期傭船契約における責任の所在は、今後も個別の契約内容や実際の運用の実態に応じて責任の所在が判断されることになります。これは形式よりも実態を重視する近年の法解釈の流れとも一致しています。
定期傭船契約は、分業化が進む海運産業において、船主と定期傭船者という責任主体を結びつける要の契約形態です。トラブル時の責任関係を明確にしておくことは、実務の安定に不可欠です。改正商法第704条(とそれ以下)は、そのための基盤を整備する第一歩であり、外航実務では依然として英国法が主流であるものの、日本籍船の増加や経済安全保障への関心の高まり、さらには国際競争力の確保といった観点からも、日本法における定期傭船の意義を今一度見直す時期に来ているといえるでしょう。
以上
※本稿は筆者の個人的な見解を掲載するものです。