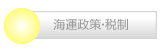2007年6月1日
社団法人日本船主協会
アジア船主フォーラム(ASF)第16回釜山総会について
2007年5月29日(火)に韓国・釜山で開催された題記総会に関するリリースおよび出席者リストを添付の通り発表致します。
以上
Tel:03-3264-7180 Fax:03-3262-4757
園田・中村
2007年5月29日
第16回アジア船主フォーラム
共 同 声 明
第16回アジア船主フォーラム(ASF)は、2007年5月28日?30日、韓国・釜山市で開催された。会合には、豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン(アセアン船主協会連合(FASA):インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの船主協会により構成)の各船主協会代表119名が出席した。韓国船主協会の会長であるJin-Bang Lee氏が会合の議長を務めた。
1992年に東京で開催された第1回ASF会合以降、ASFとその5つの‘S’委員会は、それぞれの活動を通じ国際海運界で重要な地位を確立してきた。ASFがその設立以来着実に発展してきたことを確認しつつ、会合は友好的な雰囲気の中で開催され、出席者は生産的な議論を行った。
アジア船主は、世界海運の全ての面で大きな役割を果たしている。ASFは、世界海運業界における課題に対しアジア船主が自らの意見を明確に示すべきであることを確認した。それ故、本フォーラムは、海運業界における自らの立場の強化・向上のため、アジア船主の合意された意見を国際社会に表明すべきであることに一致した。
昨年の第15回ASF総会において、出席者はASFの常設事務局を設立する強い意志を表明した。このため、常設事務局設置に係る提案を取り纏めるべくワーキング・グループ(WG)が設置された。WGは、その会合の結果を総会本会議に報告するとともに、その提案の採択を提議した。
総会本会議は、常設事務局をシンガポールに設立することに合意し、また、ASF事務局規程を採択した。この規程の下、(ASFメンバー船協会長による)会長会議が設置され、同会議に初代事務局長を選任・指名する権限が付与された。
ASFは、5つの‘S’委員会主導の下、積極的且つ効率的な方法で主要案件に対応してきた。主要案件に関する各委員会の見解と取り組みの概要は以下の通り。
- 船舶保険・法務委員会(SILC)
- ASFは、第19回SERC中間会合が2007年2月28日に沖縄で開催されたことに留意した。同委員会委員長である芦田昭充氏は、その報告の中で以下の点を強調した。
ドライバルク/タンカー部門
ドライバルク部門については、特に中国をはじめとする順調な世界経済成長を背景に、2007年の市場は着実な拡大を続けるであろうとの期待が示された。2007年及び2008年には新造船引渡し予定が減少傾向になると見られていることから、需給バランスの改善が予想される。タンカー部門については、2010年までのシングルハル・タンカーのフェーズ・アウトが如何にスムーズに行われるのか、そして、同フェーズ・アウトに関連してどの程度の新規船腹が市場に投入されてくるのかによって、将来の市況が大きく左右されるであろうということが認識された。
定期船部門の現状
太平洋トレードについては、荷動き量の増加が見込まれており、2007年は総体的によりタイトな需給関係となることが期待される。一方出席者は、特に米国内輸送費を中心に引き続く高コスト状況に対し深い懸念を示した。アジア域内トレードに関し、ASFは、力強い中国経済が引き続きアジアの好調なコンテナ荷動きを支える原動力となるであろうことに留意した。これに関連し、ベトナムにおけるコンテナ市場の急成長がアジア域内トレードにもたらす追加的な好影響に特別な注目が示された。一方で、出席者は他航路からの船腹カスケード効果により供給過剰が起こりうることに対する懸念を共有した。更には、特に燃料油価格をはじめとする高コスト状態が、船社にとってマイナス要因となっている。
アジアにおける荷主との関係
航路市況に関する荷主のより良い理解を得るために、出席者は荷主との良好な関係を促進することが不可欠であることを再確認した。これに関連し、2006年6月と11月、東京で日本政府関係者及び東京に拠点を置く荷主/船社の出席の下、「コンテナ・シッピング・フォーラム」が開催されたことが報告された。SERC会合は、アジアにおける荷主と船社間の建設的な関係を強化するため、対話に基づく最大限の努力を継続していくことで一致した。
定期船海運に対する独禁法適用除外制度
SERCメンバーは、豪州・中国・香港・日本・シンガポールにおける最近の動きに留意する一方、EUが定期船同盟に対する包括適用除外の廃止を決定したことに懸念を表明した。出席者は、健全な海運業界と増加する国際貿易需要を支えるために必要とされる投資能力とを維持するためには、独禁法適用除外制度が不可欠であり、また、除外制度は貿易業界全体に利益をもたらすものであるというASFの長年の立場を再確認した。各船社は、貿易を支える上で船社間協定が果たしている重要な役割について、政府や荷主など関係者の理解を得るための継続的な努力を行うべきであることが合意された。
ASFは、そのメンバー、特に韓国/日本/シンガポール各船主協会が、独禁法適用除外制度の廃止に反対する意見書を欧州委員会などに提出したことに留意した。その後、韓国船主協会は欧州委員会より、「同制度の柱の一つであるコンソーシア規則を維持する一方で4056/86規則は廃止するが、その代替案を準備する予定である」旨の返信を受領した。また、本フォーラムは、ASF議長として韓国船主協会が、豪州及び日本船主協会とともに日本の公正取引委員会に対し適用除外制度廃止に反対する旨の意見書を提出したことにも留意した。
パナマ運河庁(PCA)
パナマ運河庁(PCA)は、2007年2月、通航料値上げ案を発表した。提案された値上げ額は容認し難い高額なもので、特にコンテナ船・タンカー・自動車専用船のコストに重大な影響を及ぼすものである。SERC沖縄会合では、向こう3年間にわたるパナマ運河通航料値上げ提案は、より長期間に分散して実施されるべきとの考え方で一致し、ASF議長(韓国船協会長)に対し、ASFを代表して通航料値上げ案への強い反対を申し入れる意見書をPCAに出すよう求めることを決定した。ASFは、その後韓国船協がASF議長としてPCAに意見書を3月9日付で提出し、同月14日の公聴会に出席したことに留意した。また、シンガポール及び日本船主協会も、それぞれ個別に意見書をPCAに提出した。その後、PCAは4月に修正案を発表し、韓国船協はASFを代表して4月20日付でPCAに追加意見書を提出。PCAからは「ASFの意見書はPCA理事会で取りあげられるだろう」との回答を受領したことについても留意された。(注:パナマ内閣審議会は、若干修正されたPCA案を4月25日付で承認した)
その他
最近のWTOの動向が報告された。SERC会合はドーハ・ラウンド交渉の再開に歓迎の意向を示し、海運業界における現行の自由貿易慣行を成文化するため、サービス貿易に関する一般協定(GATS)に海上輸送サービスを盛り込む重要性について引き続き訴えていくよう各出席者は改めて要請された。また、会合は世界貿易に好ましい影響を与えるであろうベトナムのWTO加盟を温かく歓迎した。
アジアにおける自由貿易協定(FTA)と二国間のダイナミックな経済関係の拡大が、アジアの経済と荷動きに前向きの影響を与えていることが留意された。出席者は、こうした展開が引き続き促進されていくことへの期待感を確認した。
国際海上物品運送条約の新草案に関する最近の動向が報告された。同条約案は国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)で審議されており、主にコンテナ輸送における貨物の滅失や損傷に関する運送人の責任と賠償範囲に統一性を与えるためのものである。同条約案は、海上輸送とインダーモーダル輸送の両方を対象としている。出席者は、新条約の動向について細心の注意を払うよう要請された。
- シップ・リサイクリング委員会(SRC)
- ASFは、第10回SRC中間会合が2007年3月30日にベトナムのハノイで開催されたことに留意した。同委員会委員長であるArnold Wang氏は、その報告の中で以下の点を強調した。
シップリサイクル活動
ASFは、IMO海洋環境保護委員会(MEPC)で策定作業が行われているシップリサイクルに係る条約案および同条約に必要なガイドラインの最近の検討状況に留意した。本フォーラムは、船主、造船所、リサイクル業者、舶用業者、船級協会および政府関係者等、条約の議論に係る関係者の多大なる努力と精力的な作業に謝意を示した。
技術上の懸念
本フォーラムは、有害物質の一覧表(インベントリ)や証書の義務付けといった同条約の内容が既存船に適用されるにあたり、条約上の柔軟性を求めるとともに、リサイクル作業中に参照すべき有用かつ有益な情報として、条約で求められる船内の有害物質の一覧表の共通書式を策定することが極めて重要であることを認識した。しかしながらASFは、船主自身が一覧表を作成することは、十分な情報資源と専門知識を有しないことから、極めて困難になるであろうとの深刻な懸念を表明した。それ故、船舶建造と船舶に備え付けられる設備の専門知識を有する造船所や舶用業者などの他の関係者は、一覧表の作成において引き続き全面的な支援を行うべきである。
環境上の懸念
更にASFは、より安全かつ環境上適正なリサイクル施設の促進が非常に重要であることを認識した。この点において、ILOやIMOなどの国際機関が、シップリサイクル作業に従事する労働者の意識を高めるために、主要リサイクル国において地域セミナーを継続して開催していることが高く評価された。本フォーラムは、係る協調努力は必ず状況の改善に繋がると確信する。
安全かつ環境上適正なシップリサイクルのための国際条約
ASFは、アジアの船主が、世界の海運業界の主要プレーヤーのひとりとして、より安全で環境上適正なシップリサイクルを促進し奨励する方法を引き続き議論していくことを確認した。また、シップリサイクルには、旗国、リサイクル国、船主、造船所、舶用業者、シップリサイクル業者、船級協会など様々な関係者が関与することから、今後のIMO条約策定作業において、全ての関係者の役割が明確に定義されなければならないと強調された。
SRCの議長
ASFは、新たにNACS(台湾船主協会)の会長に任命されたArnold Wang氏が、2005年以来SRC議長を務めたNACS前会長のRobert Ho氏から同議長の任務を引き継ぐというNACSの決定を承認した。同フォーラムは、Robert Ho氏の議長としての貢献に対し心から感謝の意を表明した。
- 船員委員会(SC)
- 第12回SC中間会合が2007年1月16日香港で開催された。同委員会委員長のリ・シャンミン氏は、第16回総会に対するその報告において以下の点を強調した。
STCW条約の見直し
ASFは、IMOの船員・訓練当直基準(STW)小委員会がSTCW条約及び関連コードを改正すべきか否かについて検討するため、同条約の見直しを行っていることに留意した。世界の船員の大多数がアジア地域から供給され、かつ雇用されていることから、本フォーラムは全ASFメンバーに対し、STCW条約施行の経験を分かち合い、この見直し作業に貢献するよう要請した。
配員基準(A.890(21))の見直しと安全配員
本フォーラムは、安全配員およびIMOのSTW委員会によるA.890(21)規則見直しに関する業界内の論争について議論した。ASFは、疲労と配乗要件がどの程度関連しているかを判定するため、船種毎の実労働/休息時間について第三者による調査を行うことが必要であると認識した。
配員基準(A.890(21))の見直しと安全配員
本フォーラムは、安全配員およびIMOのSTW委員会によるA.890(21)規則見直しに関する業界内の論争について議論した。ASFは、疲労と配乗要件がどの程度関連しているかを判定するため、船種毎の実労働/休息時間について第三者による調査を行うことが必要であると認識した。
船員の募集と訓練
本フォーラムは、ASFメンバーが船員職に対する若者の関心向上に尽力していることについて謝意を持って留意するとともに、アジア地域の船舶職員候補生が増加していることに注目した。ASFは、アジア船員の訓練及び雇用に関する教育機関と船主の協力を歓迎するとともに、安全運航確保のため、伝統的なシーマンシップの重要性が強調されるべきと認識した。会合は、これらの相互協力がアジアの船員の供給と雇用の継続的促進に貢献すると考える。
船員の雇用条件
ASFは、2007年5月後半に豪州で行われたIBF協約改定の議論について留意した。これらの議論は継続的な協議の一部であり、次回は韓国の釜山で7月に予定されている。本フォーラムは、船舶運航の安全性、品質、効率性を最適化しようとする運航者への全ての干渉に対し懸念を示した。また、会合は、船員の雇用条件は船員の居住している国で協議されるべきであり、かつその国の生活水準を反映するべきものであるとの立場を再確認した。
- 航行安全および環境委員会(SNEC)
- SNEC委員長S S Teo氏は、2006年11月28日開催のSNEC第13回中間会合においてまとめられた航行安全および海洋環境保護問題に関するレポートを更新して提出した。同氏はその報告の中で以下の点を強調した。
海賊および武装強盗
ASFは、世界各地域、特にマ・シ海峡において、海賊事件の発生が減少し続けていることを歓迎した。船舶のハイジャックもまた減少傾向にあり、主に小型船が標的とされている。
こうした状況の改善に関して、ASFは、積極的にこの問題に取り組み、領海内の保安警備を向上させた国々に謝意を表した。マ・シ海峡において、本フォーラムは沿岸3カ国政府に警戒および監視に関する協力体制をさらに強化するよう要請した。また、ASFは、すべての船主に対し、油断することなく、特に夜間、海賊多発地域を航行する際は警戒を怠らないよう船長にアドバイスするよう求めた。
さらに、ASFは、日本の提案によるアジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)が2006年9月4日に発効し、シンガポールに情報共有センター(ISC)が設立されたことに留意した。ISCは、アジア海域の安全航行および船舶の保安を強化するため、16カ国から報告される海賊事件の発生を正確かつ迅速に伝えることを目的とする。本フォーラムは、その情報はReCAAPウェブサイトへの表示に加え、当該海域航行船舶に明瞭かつ迅速に伝達されるべきであるとの考えに一致した。
マラッカ・シンガポール海峡における安全、保安および環境保護の強化
ASFは、2006年9月18?20日のマ・シ海峡に関するクアラルンプール会議において公表されたIMO声明を支持した。更にASFは、沿岸国、海峡利用国、海運業界および他の関係者が、航行援助施設の管理および海洋環境保護に係る任意の基金のためのメカニズムの確立に向けて協力するべきとするSNECの考えに同意した。また、クアラルンプール会議において沿岸3カ国技術専門家グループ(TTEG)より提案された6つのプロジェクトに対して十分な支援を与えるよう、利用国および関係者に求めた。
これとは別に、2007年3月13日?14日にマレーシア海事研究所、インドネシアの東南アジア研究センター、シンガポールのエス・ラジャラトナム国際研究大学及びわが国の日本財団により、同海峡の航行援助施設および海洋環境保護のための基金創設に関して提案することを目的としたシンポジウムが開催された。
ASFは、“マラッカ海峡基金”設立の方向性を支持した。同基金は、海峡における航行援助施設の管理及び環境保護のための対策に向け、海峡利用国、海運業界および他の関係者に、任意で貢献できる機会を与えるものである。また、会合は、基金のメカニズムは公正に管理されるべきとの考えに一致した。
一方ASFは、マ・シ海峡を利用する船舶へのいかなる課金制度も支持しないことで合意した。
MARPOL条約附属書VI - 船舶による大気汚染の防止
ASFは、環境保護に関するスタンスとその努力に対する支持を改めて確認した。また、全ての船舶に残渣油から留出油への切り替えを求めるINTERTANKO提案に留意した。
本フォーラムは、(INTERTANKO提案に対する)船社の懸念に留意し、すべてのオプションについて実現可能性の検証が行われるべきことに合意した。この調査はあらゆる要因について深く検討されるべきである。
IMO第11回ばら積み液体・ガス小委員会(BLG11)において、大気汚染を最小限にする種々の戦略に関する包括的な研究を実施するため、IMO事務局長が官民合同の科学的検討グループの設置に着手していることに、ASFは留意した。
ASFはこの動きを歓迎するとともに、ロンドンで2007年7月9?13日に開催される第56回海洋環境保護委員会(MEPC56)において、全てのASFメンバー国政府がこの動きを支持するよう求めた。
- 船舶保険・法務委員会(SILC)
- ASFは、船舶保険・法務委員会の中間会合が2007年4月17日に香港で開催されたことに留意した。同委員会委員長のジョージ・チャオ氏は、その報告の中で以下の点を強調した。
船主の民事責任と金銭的保証に関するEU指令案
ASFは、欧州議会と欧州閣僚理事会で提案された船主の民事責任と金銭的保証に関する指令案の潜在的な影響について懸念を表明した。現在未発効の条約を批准するとした指令案への支持は容認するが、ASFが懸念しているのは、例えば、責任限度額まで最短の時間で被害者補償がなされることを確実にしているP&I保険の証書と責任制限の役割について混乱が生じ得ることである。またASFは、遺棄船員に関する提案は不明瞭で、新たに採択されたILO海事条約に委ねるのが最善の策とした。
しかしながら、ASFの最大の懸念は、指令案により国際海運をつかさどる保険及び法体系が非常に不安定な状態になることである。地域規制により過失の定義が地域毎に異なることにより生じる不安定要素は、全ての船舶が金銭的保証を保持する規定とあいまって、世界海運業界全体を混乱させることになる。
海難残骸物除去条約
ASFは、最近ケニアの首都ナイロビで開催された海難残骸物除去に関する外交会議で新たな条約が採択されたことを歓迎した。ASFは、喫緊の問題として、締約国が発行する1通の保険証明書によって責任と補償に関する全てのIMO関連条約を証明できる共通モデル作成をIMO締約国へ促した。しかしながら、新たな条約の進展により、殆どの海難残骸物が発生する領海で、その除去に関する統一した責任体制が創設されそうにないことを遺憾とした。
カナダ渡り鳥法
ASFは、カナダ法案C-15の採択によるカナダ渡り鳥法(1999)の改正に留意し、カナダ船主が表明した懸念を共有した。この点について、ASFは、カナダ政府に対し法律の改正を再考し、船員の人権に影響を及ぼす条文を取り消すことを検討するよう再度促した。
船舶に起因する海洋汚染に対する指令
ASFは、船舶からの故意による油濁事例全てについて改めて遺憾の意を表すとともに、既存船の運航者の責任と義務を喚起し、また、新造船および既存船に対するエンジンルームの油水管理システムに係るガイドライン改訂に尽力した様々な業界団体と国際機関の活動を支持した。本フォーラムは、2007年4月1日迄にEU加盟国で採択されることとなっていた船舶に起因する海洋汚染に係るEU指令について、海運関係団体の連合体が行った訴訟の進捗状況に留意するとともに、不慮の油濁事故へ刑事罰を課すとした指令の潜在的な影響について引き続き懸念を表明した。ASFは、EU加盟国が指令を採択するにあたり直面するであろうMARPOL条約および国連海洋法条約(UNCLOS)の条文と指令との矛盾の問題についてEU各国の注意を喚起した。
次回会合
中国船主協会副会長のZhao Huxiang氏より、第17回ASF会合を2008年5月に中国で開催するとの案内があった。開催日と場所は追って発表される。
出席者は、韓国・釜山市における第16回ASF会合での卓越した運営に対し、韓国船協会長並びにそのスタッフに謝意を表した。
注)アジア船主フォーラム(ASF)は、豪州・中国・台湾・香港・日本・韓国の船主協会、及びアセアン諸国の海運団体で構成されるアセアン船主協会連合から成る任意組織である。ASFの目的は、アジア船主業界の利益を促進することである。ASF年次総会の間には、5-S委員会(シッピング・エコノミックス・レビュー、船員、シップ・リサイクリング、航行安全および環境、船舶保険・法務委員会)により継続した作業が遂行されている。ASFの船主および船舶管理者は、世界商船船腹の50%近くを支配・運航していると推定されている。
| 第16回アジア船主フォーラム(ASF)釜山総会 日本側出席者 | |
| 2007年5月29日 於:釜山 The 16th Asian Shipowners' Forum in Busan, Korea on 29 May 2007 |
|
| 氏 名 Name |
役職名(船協 / 会社) Title (JSA / Company ) |
| 鈴木 邦雄 Kunio SUZUKI |
日本船主協会 会長 (商船三井 会長) President, JSA (Chairman of the Board, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 宮原 耕治 Koji MIYAHARA |
日本船主協会 副会長 (日本郵船 社長) Vice President, JSA (President, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) |
| 前川 弘幸 Hiroyuki MAEKAWA |
日本船主協会 副会長 (川崎汽船 社長) Vice President, JSA (President & CEO, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.) |
| 杉山 暎一 Eiichi SUGIYAMA |
日本船主協会 副会長 (新日本石油タンカー 社長) Vice President, JSA (President, Nippon Oil Tanker Corporation) |
| 芦田 昭充 Akimitsu ASHIDA |
日本船主協会 常任理事(商船三井 社長) Executive Director, JSA (President, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 宇佐美 皓司 Koji USAMI |
日本船主協会 副会長 Vice President, JSA |
| 薬師寺 正和 Masakazu YAKUSHIJI |
日本船主協会 政策委員会副委員長 (商船三井 専務執行役員) Vice Chairman of Policy Committee (Director/Senior Managing Executive Officer, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 高橋 秀幸 Hideyuki TAKAHASHI |
日本船主協会 国際幹事会幹事 (新日本石油タンカー 取締役業務部長) Member of International Sub-Committee, JSA (Director & General Manager, Business Coordination Dept. Nippon Oil Tanker Corporation) |
| 佐々木 真己 Masami SASAKI |
(川崎汽船 執行役員) (Executive Officer, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.) |
| 中本 光夫 Mitsuo NAKAMOTO |
日本船主協会 理事長 Director General, JSA |
| 井上 登志仁 Toshihito INOUE |
日本船主協会 会長秘書 (商船三井 経営企画部部長代理) Secretary to the President, JSA (Deputy General Manager, Corporate Planning Division, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 新井 真 Makoto ARAI |
日本船主協会 環境幹事長・解撤幹事長 (川崎汽船 経営企画グループ長補佐) Chairman of Environment Sub-C'ttee, Ship Recycling Sub-C'ttee (Senior Managing Director, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.) |
| 半田 收 Osamu HANDA |
日本船主協会 常務理事海務部長 Managing Director, JSA |
| 園田 裕一 Yuichi SONODA |
日本船主協会 企画部長 General Manager, Planning Division, JSA |
| 山脇 俊介 Shunsuke YAMAWAKI |
日本船主協会 海務部副部長 Deputy General Manager, Marine Division, JSA |
| 中村 憲吾 Kengo NAKAMURA |
日本船主協会 企画部係長 Assistant Manager, Planning Division, JSA |
以 上 |
|