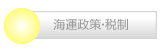2008年6月6日
社団法人日本船主協会
アジア船主フォーラム(ASF)第17回ボアオ(海南島)総会について
2008年6月3日(火)にボアオ(海南島・中国)で開催された題記総会に関するリリースおよび出席者リストを添付の通り発表いたします。
以上
Tel:03-3264-7180 Fax:03-3262-4757 本澤
2008年6月3日
第17回アジア船主フォーラム 共同声明
第17回アジア船主フォーラム(ASF)は、2008年6月2日?4日、中国(海南島)のボアオで開催された。会合には、豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン(アセアン船主協会連合(FASA):インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの船主協会により構成)の各船主協会代表132名が出席した。中国船主協会の会長であるWei Jiafu氏が会合の議長を務めた。同会合終了後に、ラウンドテーブルを構成する国際海運団体(ICS、BIMCO、INTERTANKO、INTERCARGO)の事務局長との意見交換が行われた。
会合の冒頭、出席者は2008年5月の中国・四川省大地震およびミャンマー・サイクロンの犠牲者に黙祷を捧げた。ASFメンバーの各国船主協会は、自らの加盟船社に対し、被害者救済のために支援および貢献すべく最大限可能な努力を行うよう奨励することに合意した。
アジア船主は、世界海運の全ての面で大きな役割を果たしている。ASFは、海運業界におけるその立場の強化・向上のために、世界海運に影響を及ぼす重要な事項について、アジアの船主が、国際社会に対し自らの意見を協調かつ合意に基づく方法でさらに一層表明しなければならないことに一致した。ASFはまた、アジア船主の意見をIMOを含む国際場裡での議論に反映すべく、その加盟船主協会に対し、ASFの意見を自国政府に明確に提出するよう求めることを再確認した。
昨年の第16回ASF総会において、出席者はASFの常設事務局をシンガポールに設置することに合意するとともに、同事務局規定を採択した。同規定に基づき、(ASFメンバー船協会長による)会長会議が組織され、同会議に初代ASF事務局長を2007年7月に選任・指名する権限が付与されるとともに、同年10月に常設事務局が設置された。
ASFは、5つの‘S’委員会を通じ、積極的かつ効率的な方法で主要案件に対応してきた。会合で強調された主要案件に関する各委員会の見解と取り組みの概要は以下の通りである。
シッピング・エコノミックス・レビュー委員会(SERC)
ASFは、第20回SERC中間会合が2007年11月21日に台北で開催されたことに留意した。同委員会委員長である芦田昭充氏は、その報告の中で以下の点を強調した。
世界経済
会合は、米国のサブプライムローンによる混乱を誘因とする不確実性が、世界経済に広がっていることに留意した。出席者は、現実的な市場展望に基づかない(過剰)反応を慎しみ、世界経済の動向を注意深く見守るよう要請された。
ドライバルク/タンカー部門
ドライバルク部門については、特に中国の鉄鉱石輸入の激増による荷動き量の大幅増加などを要因として、前例のないほどに高水準にあることが報告された。出席者は、近い将来に市況に悪影響を及ぼし得る経済要因が現れる可能性は低いものと思われるとの見解で一致した。タンカー部門については、原油価額の高騰と米国のエネルギー需要の低迷により、市況は2007年通年では弱含みで推移したが今年初めから急騰を見せたことが留意された。
定期船部門の現状
太平洋トレードについては、2007年上半期における全体の貨物量は前年比約7%増加を示し、同年下半期のトレードは、主に住宅関連貨物の低迷によってマイナス成長を示した。その結果、通年のトレード成長率は1%増となった。アジア域内トレードに関しては、東・西アジアにおける荷動きの伸びにより、市況は堅調な成長を維持した。
出席者は、上記航路における定期船市況の現在の運賃水準では、特に燃料コストや港湾混雑といった劇的なコスト増を補填し、過去の投資を回収し、ならびに将来必要となる投資を促進するのに不十分であるという重大な懸念を表明した。会合では、各顧客から求められている効率的なサービス水準を維持するためには、アジアコンテナ船社のCEOは、これら問題に対処する必要があることが強調された。
定期船海運に対する独禁法適用除外制度
アジアの様々な国およびEUにおいて、外航船社間協定(特に船腹共有協定および運賃協議協定)に対する独禁法適用除外制度の見直しが行われていることが留意された。出席者は、特にインドにおける不確実な状況に対し重大な懸念を表明した。SERCメンバーは、上記の国の関係者が健全な国際定期船海運のためには適用除外制度が重要であることを正しく理解するよう支援するため、必要とされる行動をとるべきことに合意した。
その他 出席者は、米国向けの全てのコンテナについて、2012年7月までに外国の積出し港で100%のセキュリティー・スキャニングを実施するよう求める同国の要件は、全コンテナを船積み前にスキャニングすることの実行可能性および検査装置の入手可能性など多大な実施上の疑問を投げかけるものである、との懸念を表明した。
上記の項目は、前回のSERC台北中間会合における報告と現状に関連して留意されたが、出席者は、世界経済の減速および継続的な燃料油高騰などの最近の問題に対しても柔軟に対応する必要があることを再確認した。
シップ・リサイクリング委員会(SRC)
ASFは、SRC第11回中間会合が2008年3月10日にインドネシア・ジャカルタで開催されたことに留意した。同委員会の委員長であるArnold Wang氏は、報告の中で次の点について強調した。
シップリサイクルに関する取り組み
ASFは、IMO海洋環境保護委員会(MEPC)で検討中のシップリサイクル条約および同条約の下で必要なガイドラインの最近の検討状況について集中的に議論を行った。安全かつ環境上適切なシップリサイクルは、シップリサイクル施設、船主、造船所、舶用業者および関係国政府など全ての関係者が協調努力しつつ積極的に追求すべきものであることを確認した。船舶のシップリサイクル施設への円滑な移動を実施するためには、複雑でないシップリサイクル手続きが策定されるべきである。
環境に関する懸案事項
ASFは、有害物質インベントリ(一覧表)作成に関するガイドライン案に従い、日本政府が船舶のインベントリ作成実験を実施中であることに留意した。同実験の結果に基づいて修正されたインベントリ・ガイドライン案がMEPC58に提出されることとなる。ASFは、有害物質のインベントリに関する共通の様式を作成することの高い重要性を認識すると同時に、インベントリの作成には、船主がその作成にあたっての十分な情報資源と専門知識を有しないことから、船舶の建造や設備に関する専門的な知識を有する政府、船級協会、造船所、舶用業者の全面的な関与が必要であることを確認した。またASFは、主としてシップリサイクル施設の管理、運営、監査および第三者認証を扱うISO30000シリーズの規格が、シップリサイクル条約とそのガイドラインの作成に関するIMOの活動と重複していることに懸念を表明した。シップリサイクル施設に関する同ISO規格は、同条約案と付属のガイドラインと同じ分野にわたっている。このためASFは、シップリサイクル施設やシップリサイクル国などの関係者が、基礎となる文書としてどの規格/ガイダンス/ガイドラインを参照するべきなのか混乱と疑問を持つ怖れがあるダブルスタンダードは避けるべきであるということに合意した。
安全かつ環境上適正な船舶のリサイクルのための国際条約
ASFはシップリサイクル条約の今後の検討に関する作業計画に留意した。同計画では条約最終案が2008年10月に香港で開催されるMEPC58に提出され、条約採択のための外交会議開催が2009年5月に予定されている。アジア船主は国際海運業界の主要な関係者として、より安全かつ環境上適切なシップリサイクルを船主が推進するための方策について引き続き議論していくことを確認した。
船員委員会(SC)
第13回SC中間会合が2007年12月6日中国・舟山で開催された。同委員会委員長のリ・シャンミン氏は第17回ASF総会への報告書において次以下の点を強調した。
船員の募集及び訓練
ASFは、船員獲得の為の激しい競争を引き起こし、船員の雇用市場に船員の引き抜き合戦を含む歪をきたした、アジア地域の船員雇用市場の需給の不均衡について深い懸念を示した。ASFは、こうした競争は、現在の船員不足への解決策を見出すことにつながらず、また、船主は船員数の増加や船員の資質向上のために、若者が船員に職業としてつくことを奨励し、彼らの発展を支援する為に努力を傾注すべきと考えた。出席者は、より多くの若者が船員になるよう誘導する政府及び海運会社の奨励制度が多くの国で設けられており、大部分のメンバーの国や地域において、船員数が昨年と比較して増加したことについて謝意を持って留意した。
STCW95条約の見直し
ASFは、IMOにおけるSTCW条約の包括的な見直しの進捗状況について留意し、STW小委員会WGの尽力を高く評価した。世界の船員の大多数が当地域から供給され、かつ雇用されていることから、ASFはSTCW95の施行に際しての自らの経験に基づき、かつ将来のIMO会議で、自らの政府と共同して活動することを以って、この見直しが体系的でかつ組織的に行われるとともに当地域の海運業界と政府の利益が最大限に反映されるよう、見直しに積極的に参加し貢献するようにASFメンバーに奨励した。
2006年ILO海事労働条約
ASFは、ILOの海事労働条約を促進する努力について留意し、ハイレベル三者調査団が各国/地域を訪れた際にASFメンバーが必要な援助を提供したことを評価した。ASFは、ILO海事労働条約の最終的な批准に向けての進捗状況および同条約が遅くとも2010年ないし2011年に発効するという予測について喜びを持って留意した。ASFメンバーは、各国政府の同条約の早期批准を奨励していくことに同意した。
航行安全および環境委員会(SNEC)
SNEC委員長 S. S. Teo氏より、2007年11月30日バンコクにおいて開催されたSNEC第14回中間会合での議論を踏まえ、航行安全および海洋環境保護の問題に関する最近の状況について報告があり、以下の問題について討議された。
海賊および武装強盗
ASFは、2007年から2008年第1四半期にかけて、世界各地域の海賊および武装強盗事件が増加していることに留意した。この増加は、ソマリアおよびナイジェリアにおける発生件数が顕著に増加したこのことに大きく起因している。アフリカ地域は現在、世界総数の50%以上を占め、世界で最も危険な地域にランクされている。
ASFは、アジア水域における海賊事件が2007年に著しく減少したことに留意した。さらに会合は、インドネシア、マレーシア、シンガポールの沿岸3カ国による空軍/海軍合同による継続的なパトロール、および海賊発生傾向にある海域を航行する船舶が実施する監視・予防策の増加により、東南アジアの海賊事件は概ね抑止されていることに留意し、これを歓迎した。
会合は、海賊発生海域-特にソマリアおよびナイジェリア-を航行する際は常時警戒するよう、全ての船舶へ注意喚起した。
長距離船舶識別装置 (LRIT)
ASFは、IMOにおいてLRITの実施に関するいくつかの重要事項が決定されたこと、およびLRITに関する規則が2008年1月1日に発効し、同年12月31日に施行されることに留意した。
LRITシステムの下、各船舶はLRIT情報を送信するためのデータセンターとの連携が求められる。そうしたことから、旗国には、NDC(国内データセンター)またはRDC(地域データセンター)を設置すべきかどうかを決定することが求められる。いくつかの旗国がグループとなって設置するCDC(協同データセンター)のような代替措置もまた可能であることが留意された。
SNECは、旗国が自身のデータセンターを設置しない場合、船主に影響を及ぼす可能性があることに十分自覚する必要があることを会合において強調した。このような状況の下、旗国は、他国政府または民間企業を通じ、既存データセンターと連携することを模索しなければならないであろう。これが不調に終わった場合、船主自身が、国または民間のサービス提供者と連携して解決策を模索しなければならない。この場合、データ送信費用は船主負担となる可能性もある。
これを踏まえASFは、全ての船主に対し、LRIT規則の下での義務が確実に満足されることを確保するため、それぞれの旗国の主管庁と直接に連絡を保つよう強く要請した。
MARPOL条約附属書VI - 船舶による大気汚染の防止
ASFは、IMO第57回海洋環境保護委員会(MEPC57)が燃料油中の硫黄分の上限規制について合意したことに留意した。同規制は、2008年10月に開催されるMEPC58において採択に向け審議されることとなっている。
ASFは、同規制の設定された基準が最終目標であり仕様的でないこと、時間をかけて実施されるもので、必要な調整や改造を行う時間を全ての関係者に与えていることについて評価した。明確に定義された短期的・長期的目標により、さらなる技術革新が奨励・促進され、実行的かつ全体的な排出削減技術および他の代替策につながることが期待される。
ASFは、全ての関係者がMARPOL条約附属書VI規則改正案への合意に達したことについて、MEPCを評価するとともに、大気・海洋環境保護のために率先して行っている種々のことに関し、アジア船主の声を上げていくことの強い責任を再確認した。
温室効果ガスの削減
SNECは、温室効果ガス(GHG)― 特に二酸化炭素(CO2)の排出に関し、IMOは緊急に取り組む必要があることを報告した。
ASFはさらに、2008年6月23日?27日の間、オスロにおいてIMO GHG中間会合が開催され、GHG削減に関する技術的および運用上の手法、さらには市場原理に基づく手法について議論されることに留意した。多くの短期的、長期的対策のうち、CO2排出ベースラインの設定方法、CO2設計指標およびデンマークによる世界的規模のバンカー課徴金スキーム提案やCO2排出量取引など、の市場原理に基づく対策について検討が進められる。
会合は、世界の海上荷動き量が将来的に拡大することを考慮し、海運業界にとって適切なGHG削減対策が構築されるようIMOに求める。
水先人 ― 能力の不足および責任
海上輸送事業において、責任ある船主の多くは、自らの船長に対し航行安全に関する高い基準を採用し実行している。しかしながら、ASFは、水先人乗船中における海難が増加傾向にあることに懸念を示した。最近、この問題は、資格のある人材の深刻な不足により複雑になってきている。
水先人は、乗船中の船舶において操船チームの重要な構成員である。それは、水先人が、港内および水路の操船を船長にアドバイスする際の意思決定の過程で重要な役割を担っているからである。不幸にも海難が発生した場合、通常、水先人はアドバイザーとして見なされ、多くの場合責任を負わない。
会合は、船舶の操船において、水先もまた人的要因と見ることができる部分であり、それ故に、操船チームへ与えられるアドバイス/決定において、水先が人的要因やヒューマンエラーのリスクに影響されやすいものと考えている。さらに会合は、水先人の基準や訓練においてIMO決議A.960(23)(水先人のための訓練・証明および運用手順に関する勧告)が厳守されるべきことに同意した。
ASFは、水先人の過失および水先人の資格証明/説明責任の問題について、IMOにおいて真剣に検討されることが急務であると考えている。
船舶保険・法務委員会(SILC)
ASFは、SILC第13回中間会合が、2008年4月8日、香港において開催されたことに留意した。欠席のジョージ・チャオ委員長に代わり、本委員会事務局が報告のなかで次の問題に焦点をあてた。
UNCITRAL国際海上物品運送法条約草案
会合は、今年1月にUNCITRAL(国連国際商取引法委員会)作業部会で合意された新たな国際海上物品運送法条約の草案に留意し、ICS、BIMCOおよび国際P&Iグループがここ数年間に亘り海運業界を代表して困難かつ緻密な作業を行ってきたことに深く感謝の意を表明した。
同草案は、今年6月、7月に開催される第41回UNCITRALで更に審議が行われることとなっており、そこで更に改正される可能性も残っている。出席者は、第61条の責任レベルに関する本委員会の懸念に留意した。同責任レベルは、ヘーグ・ヴィスビー・ルールやハンブルグ・ルールのレベルを上回り、過去のクレイム・レコードの検証から正当化された理由ではなく、全く別の理由から合意されたように見うけられる。本委員会では、この責任制限の提案は、一部の国、とりわけアジアの国にとっては条約批准への障害となる惧れがあると見ている。
HNS条約
危険物質及び有害物質の海上輸送に関連する損害についての責任並びに損害賠償及び補償に関する国際条約(HNS条約)は1996年にIMOで採択されたが、批准国数が発効要件に達していないため未だ発効されていない。会合は、同条約への関心が低かった理由、ならびに懸念を多少なりとも解決しかつ批准を促進することを目的に、国際油濁補償基金総会の下に設置されたHNS Focus Groupにより条約改正の議定書案が作成されたことに留意した。
出席者は、同条約の早期批准が海運業界の関心事であること、および上記解決策が国際的な制度であり、かつ船主と貨物関係者との責任分担の原則が弱められないことを条件に議定書案を支持することに合意した。
バンカー条約
燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)が2008年11月21日に発効する。同日以降、条約締約国に登録、または締約国の港に入出港する1,000G/T以上の船舶は、締約国が発行する金銭的保証の証書を備え付けなければならない。
証書を必要とする船舶の数は非常に膨大であるが、条約を批准しているのは20カ国にすぎないため、出席者は、締約国と国際P&Iグループ双方に対し、締約国で貿易を行う船舶へ関連証書を発行する必要性について早急に取り組むことを促した。
JWCの危険区域リスト
ASFは、Joint War Committee(JWC)が船舶戦争保険の除外水域リストの見直しを行い、2008年5月2日付でリストの改正を公表したことに留意した。会合は、同リストにあるアジアの複数の水域で船舶に対する襲撃が減少していること、およびセキュリティの向上が図られたことを考慮し、JWCに対し、そうした水域を継続的にリストに入れることを再考するよう求めるものである。
この関係で、ASFはJWCに対して、リストを改正するにあたっては、定期的に業界の代表と会合を開き、可能であれば、業界と対話することを改めて要請した。
次回会合
第18回ASF会合は、2008年5月25?27日に台南のエバーグリーン・プラザ・ホテルで開催される。
出席者は、中国・ボアオにおける第17回ASF会合での卓越した運営に対し、中国船協会長ならびにそのスタッフに謝意を表した。
以上
注)アジア船主フォーラム(ASF)は、豪州・中国・台湾・香港・日本・韓国の船主協会、及びアセアン諸国の海運団体で構成されるアセアン船主協会連合から成る任意組織である。ASFの目的は、アジア船主業界の利益を促進することである。 ASF年次総会の間には、5つのS (5-S)委員会(シッピング・エコノミックス・レビュー、船員、シップ・リサイクリング、航行安全および環境、船舶保険・法務委員会)により継続した作業が遂行されている。ASFの船主および船舶管理者は、世界商船船腹の50%近くを支配・運航していると推定されている。
| 第17回アジア船主フォーラム(ASF)釜山総会 日本側出席者 | |
| 2008年6月3日 於:ボアオ (海南島、中国) The 17th Asian Shipowners' Forum in Boao, China on 3 June 2008 |
|
| 氏 名 Name |
役職名(船協 / 会社) Title (JSA / Company ) |
| 前川 弘幸 Hiroyuki MAEKAWA |
日本船主協会 会長 (川崎汽船 社長) Vice President, JSA (President & CEO, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.) |
| 宮原 耕治 Koji MIYAHARA |
日本船主協会 副会長 (日本郵船 社長) Vice President, JSA (President, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) |
| 芦田 昭充 Akimitsu ASHIDA |
日本船主協会 副会長 (商船三井 社長) Executive Director, JSA (President, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 杉山 暎一 Eiichi SUGIYAMA |
日本船主協会 副会長 (新日本石油タンカー 社長) Vice President, JSA (President, Nippon Oil Tanker Corporation) |
| 飯塚 孜 Tsutomu IIZUKA |
日本船主協会 副会長 Vice President, JSA |
| 薬師寺 正和 Masakazu YAKUSHIJI |
商船三井 副社長 (Executive Vice President, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) |
| 高橋 秀幸 Hideyuki TAKAHASHI |
日本船主協会 国際幹事会幹事 (新日本石油タンカー 取締役業務部長) Member of International Sub-Committee, JSA (Director & General Manager, Business Coordination Dept. Nippon Oil Tanker Corporation) |
| 佐々木 真己 Masami SASAKI |
(川崎汽船 執行役員) (Executive Officer, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.) |
| 中本 光夫 Mitsuo NAKAMOTO |
日本船主協会 理事長 Director General, JSA |
| 半田 收 Osamu HANDA |
日本船主協会 常務理事・海務部長 Managing Director, JSA |
| 園田 裕一 Yuichi SONODA |
日本船主協会 常務理事・企画部長 General Manager, Planning Division, JSA |
| 山脇 俊介 Shunsuke YAMAWAKI |
日本船主協会 海務部副部長 Deputy General Manager, Marine Division, JSA |
| 本澤 健司 Kenji HONZAWA |
日本船主協会 企画部係長 Assistant Manager, Planning Division, JSA |
以 上 |
|